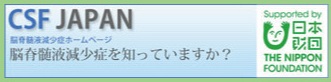本文
脳脊髄液減少症について
脳と脊髄の外側は硬膜という膜におおわれており、この硬膜と脳脊髄の間は、脳脊髄液(髄液)という透明な液体で満たされています。「脳脊髄液減少症」は、この脳脊髄液が減少することにより、頭痛、めまい、倦怠感など様々な症状を呈する疾患です。交通事故やスポーツ外傷など、体への強い衝撃を受けて硬膜が傷つき、そこから脳脊髄液が漏れ出すことが原因となる場合もあれば、明らかな原因がなく発症することもあります。
「低髄液圧症」、「脳脊髄液漏出症」と表されることもあります。
主な症状
起立性頭痛(立位によって増強する頭痛)などの頭痛、頚部痛、背部痛、腰痛、めまい、吐き気、倦怠感、易疲労感、不眠、記憶障害、集中力低下、聴覚障害、視覚障害、羞明感などが報告されています。これらの症状は、起立・座位で悪化しやすい、天候・気圧の変化の影響を受けやすいといわれています。
医療機関の受診について
上記のような症状があり、脳脊髄液減少症が心配なときは、医療機関を受診して正確な診断を受けることが大切です。自覚症状だけでは他の疾患との区別がつきません。すぐに治療できる病気の可能性もありますし、持病の悪化や他の重い病気の可能性もあります。
脳脊髄液減少症の診断には、脳神経に詳しい医師による診察と、脳の画像検査などの精密検査が必要です。普段の体調を良く知るかかりつけ医や、神経内科(脳神経内科)、脳神経外科を標榜する医療機関へご相談ください。
なお、群馬県では医療機関(神経内科・脳神経内科、脳神経外科等を標榜する医療機関)の協力を得て、脳脊髄液減少症の診療等に関するアンケートを実施しました。診療等が可能と回答した医療機関のうち、公表に同意をいただいた医療機関について以下のとおり公表いたします。
《留意事項》
- ここに掲載されていない医療機関では、相談・診療を受けられないということではありません。
- 受診の際は、必ず事前に医療機関にお問い合わせください。
- 検査や治療方法は担当医師の判断により決定されます。希望する検査や治療が必ず受けられるということではありません。
- 掲載されているデータは調査時時点のものとなります。
治療方法について
患者さんの状態に応じて、医師がご本人と相談して治療方針を決定します。担当医師とよく御相談ください。主な治療法として以下が知られています。
- 保存的治療:安静、生活指導など
- ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法):患者自身の血液を硬膜外に注入し髄液が漏れている部分を塞ぐ方法。平成28年4月1日より施設基準の届出を行った医療機関で保険診療の適応。
関連リンク
脳脊髄液減少症に関する研究成果、関連通知、関係団体等をご案内します。
- 厚生労働省 「脳脊髄液減少症」の研究について<外部リンク>
- 文部科学省 学校保健の推進(いわゆる脳脊髄液減少症に関するもの)<外部リンク>
- 群馬県難病相談支援センター<外部リンク>
- 認定特定非営利活動法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会<外部リンク>
- 脳脊髄液減少症患者支援の会 子ども支援チーム<外部リンク>
- CSF JAPAN 脳脊髄液減少症 ホームページ(※以下のバナーをクリックしてください。)