本文
令和4年度土壌流亡対策担当者会議を開催しました
要約
嬬恋村のキャベツ産地で問題となっている土壌流亡について、関係機関で対策会議を開催しました。それぞれの機関で取り組んでいる内容について共有し、協力体制を確認しました。
1.ねらいと背景
嬬恋村を中心としたキャベツ産地では、多くのほ場が傾斜地にあり、産地形成以来台風やゲリラ豪雨などでほ場の表土が侵食されてきました。その結果、近年では一部で表面の黒ボク土が流失し、下層土が露出しているほ場が散見されるようになってきました。そういったほ場では、キャベツの生育が悪く、生産が不安定になっているのが現状です。
そこで、土壌流亡について取り組んでいる関係機関の情報を持ち寄り、内容を共有するとともに、それぞれが連携・協力して土壌流亡対策にあたるため、土壌流亡対策担当者会議を開催しました。
2.取り組み成果
2月3日にJA嬬恋村の会議室において会議を開催し、JA嬬恋村営農畜産課、嬬恋土地改良区、嬬恋村役場、県からは技術支援課、農業技術センター土壌保全係、高冷地野菜研究センター、吾妻農業事務所普及指導課から計15名が参加しました。
会議では、JA嬬恋村から緑肥(エン麦・ライムギなど)の栽培面積の推移、技術支援課からドローンを使った空撮による現在と平成17年のほ場表面の比較、農業技術センターからは土壌中の可給態窒素量に基づく適正施肥マップ作成や、沈砂地土壌の利用関連の研究結果、そして普及指導課から下層土露出ほ場での実証ほの結果とグリサポ事業で取り組んだGPSソワーによる可変施肥について等、それぞれの機関で取り組んだ土壌流亡対策の説明が行われた後、情報交換が行われました。
今年度は、種子価格が高騰したため、緑肥の販売金額は増加したものの販売量は減少したことや、沈渣地の土壌では立ち枯れ性病害のリスクが確認できたこと、施肥マップとスマートフォン、GPSソワーを組み合わせた可変施肥の可能性等が紹介され、情報共有されました。
3.今後の方向
今後は、各関係機関の取り組みを協力しながら行っていきます。取り組んだ内容は、同様の会議を開催し、情報共有を図り、土壌流亡対策に活かします。
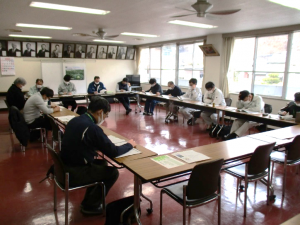
検討の様子








