本文
就農支援策
就農に向けた支援制度を紹介します。
1 ファームトレーニング事業
本県での就農を希望し、就農希望地の市町村で十分な就農相談を行った研修者に対して研修機会を提供することで、円滑な就農を促進することを目的としています。受入れ農家については、研修者の希望に合致した受入れ農家を農業事務所が選定して依頼します。
(1)事業の内容
- 研修者を受け入れる農家等(農業事務所が選定した者に限る)に対して研修指導経費の一部を支援します。
- 受入枠は予算に応じ、年度ごとに定めています。
(2)要件
以下に掲げる要件を満たす場合に事業費を交付します。
ア)研修受入れ農家等
次のいずれかであることが要件です。
- 群馬県農業経営士(名誉農業経営士を含む)
- 5年以上の農業経験を有し、研修受入体制の整っている青年農業士
- 農業経営基盤強化促進法における認定農業者
- 第三者への農業経営の移譲を希望する農業者
イ)研修者
次のすべてを満たすことが必要です。
- 青年等就農計画を作成した認定新規就農者もしくは認定新規就農者の申請を予定している者、又は本県で就農相談を行い、就農計画を作成した者。(「本県で就農相談を行い、就農計画を作成した者」とは、農業経営開始予定時の年齢が18歳以上65歳未満の者で、就農計画書の経営目標が市町村の基本構想と照らして適切であること)
- 原則として県内に居住し、研修終了後、青年等就農計画(または就農相談を行い、作成した就農計画)の計画期間内に群馬県内で自ら農業経営を開始することが確実な者。
- 研修受入農家が自主的に募集した研修者ではないこと。
- 研修受入農家と過去に雇用関係が無いこと。また、研修期間中に研修受入農家等から労働の対価の支払いがないこと。
- 研修期間中に研修受入農家から労働の対価の支払いがないこと。
ウ)研修
次のすべてを満たすことが必要です。
- 研修計画に基づいて行う研修であること。
- 青年は概ね12月、中高年齢者は原則6月以上受ける研修であり、かつ月日数の2分の1以上は受入農家等の研修指導を受けること。
2 就農準備資金・経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
(1)就農準備資金
就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける方に対し、資金を交付します。
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有してること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
- 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて障害保険に加入すること
(2)経営開始型
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。
- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
- 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること) - 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの - 人・農地プランへの位置づけ等
市町村が作成する 人・農地プラン(農林水産省)<外部リンク>(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと - 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
詳しくはこちら「就農準備資金・経営開始資金」(農林水産省)<外部リンク>
3 農業制度資金
(1)青年等就農資金「新規就農者向けの無利子資金制度」(農林水産省)<外部リンク>
就農に当たっての準備に必要な経費、農業経営を開始する際に必要な設備・機械の購入や運転資金などに利用できる無利子の資金です。
- 対象者 認定新規就農者
- 借入限度額 一般3,700万円(特認1億円)
- 償還期限 17年以内(うち据置期間5年以内)
(2)その他の農業制度資金
農業近代化資金「農業制度資金早わかり表」
・認定新規就農者等が施設の取得等に幅広く使える資金です。
経営体育成強化資金(日本政策金融公庫)<外部リンク>
・認定新規就農者等が施設の取得等に幅広く使える長期の日本公庫資金です。
農林漁業セーフティネット資金(農林水産省)<外部リンク>
・農業経営の維持安定が困難な農業者を対象に、一時的な影響に対し、緊急的に対応するために必要な長期かつ低利な資金。
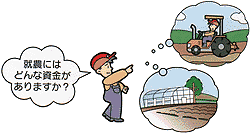
農業制度資金の詳細はこちら「農業制度資金早わかり表」
4 雇用就農資金
雇用就農者の確保・育成を推進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成します。また、農業法人等がその職員等を次世代の経営者として育成するために国内外の先進的な農業法人や異業種の法人へ派遣して実施する研修を支援します。
雇用就農資金には以下の3タイプがあります。
(ア)雇用就農者育成・独立支援タイプ
(イ)新法人設立支援タイプ
(ウ)次世代経営者育成タイプ
詳しくはこちら。農林水産省ホームページ<外部リンク>、農業をはじめる.JP<外部リンク>。
まずは、就農を希望する市町村役場の農業担当窓口へ御相談ください。








