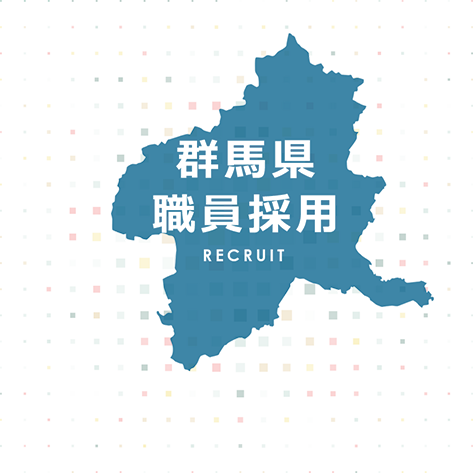本文
よくある質問(県職員採用)
試験関係
質問:県職員になるにはどうしたらいいですか。
質問:各試験の募集人数について教えて下さい。
質問:受験案内の入手方法を教えてください。
質問:栄養士、保育士・児童指導員、犯罪鑑識員などの職種は、募集していますか。
質問:看護師の募集はありますか。
質問:車椅子で試験を受験することはできますか。
質問:試験の併願はできますか。
質問:第1次試験会場への交通手段は自動車でもよいでしょうか。
質問:1次試験もスーツで受験するべきでしょうか。
質問:試験に出席できなくなった場合、欠席の連絡は必要ですか。
質問:就職説明会を実施しているのであれば、参加したいのですが。
質問:性別や出身地等による有利・不利はありませんか。
質問:採用試験の受験資格に学歴は必要ですか。
質問:過去の試験問題は公表されていますか。
採用・配属
質問:最終合格をしても、採用されない場合がありますか。
質問:配属先について教えてください。
給与・勤務条件
質問:勤務時間等について教えてください。
質問:初任給について教えてください。
研修制度
質問:研修制度はどのようなものですか(知事部局の例)
質問:メンター制度はどのようなものですか(知事部局の例)
試験関係
質問:県職員になるにはどうしたらいいですか。
回答:群馬県の職員になりたい人は、人事委員会が実施する採用試験(選考考査)を受けてください。なお、教員や会計年度任用職員などは実施方法が異なります。教員の選考試験は教育委員会、市町村職員の採用試験は各市町村等が実施していますので、直接問い合わせてください。
質問:各試験の募集人数について教えて下さい。
回答:募集人数は、各試験の「受験案内」でお知らせします。(受験案内のホームページ掲載日は、令和7年度群馬県職員採用試験日程・受験資格のページに公表しています。)
質問:受験案内の入手方法を教えてください。
回答:インターネットを利用できる方は、県職員・警察官採用情報ホームページから受験案内を確認してください。受験案内を確認できない方は、郵送で受験案内を請求することができます。→入手方法について
質問:栄養士、保育士・児童指導員、犯罪鑑識員などの職種は、募集していますか。
回答:職員の欠員がある場合に、選考考査という試験区分で募集を行います。
質問:看護師の募集はありますか。
回答:県立病院の看護師の募集は、病院局で行っています。詳細は病院局経営戦略課のページで確認してください。
質問:車椅子で試験を受験することはできますか。
回答:警察官試験を除き、車椅子での受験は可能です。受験申込時にその旨ご連絡ください。
質問:試験の併願はできますか。
回答:1類試験(行政事務B・総合土木B)を除き、受験資格に該当し、試験日が異なる試験であれば、複数受験することも可能です。なお、1類試験(行政事務B)を受験した方は、その他の1類試験(全試験区分)を、1類試験(総合土木B)を受験した方は総合土木Aを除くその他の1類試験を受験することはできません。
質問:第1次試験会場への交通手段は自動車でもよいでしょうか。
回答:自動車での来場は固く禁止します。試験会場及びその付近には受験者用の駐車場はありません。また、自動車による送迎も付近の道路が渋滞し、遅刻の原因ともなりますので、なるべく避けてください。やむを得ず自動車による送迎となる場合も、会場周辺は道路も狭く送迎車の駐停車は近所の迷惑となりますので、ご家族の方等も会場周辺で駐停車して待機することは絶対に避けてください。また、試験会場を間違える受験者も毎年見受けられます。必ず、受験票に記載された会場とその場所を確認してください。
質問:1次試験もスーツで受験するべきでしょうか。
回答:スーツの着用は不要です。あなたの本領を発揮するためにも、身軽な服装で受験してください。
質問:試験に出席できなくなった場合、欠席の連絡は必要ですか。
回答:第2次試験以降の試験を欠席される場合は、電話やメール等による事前連絡をお願いします。
また、欠席の場合は、できる限り早い段階でご連絡ください。
なお、第1次試験を欠席される場合は、事前連絡は不要です。
質問:就職説明会を実施しているのであれば、参加したいのですが。
回答:日程等の詳細については、こちらでご確認ください。また、説明会の動画をこちらに掲載しています。
質問:性別や出身地等による有利・不利はありませんか。
回答:採用試験は、地方公務員法の平等の取扱の原則に基づき実施しています。性別や県外・県内出身の別などによって、有利、不利が生じることはありません。
質問:採用試験の受験資格に学歴は必要ですか。
回答:各試験の受験資格は一部(警察官試験、選考考査(獣医師・薬剤師などの資格職)等)を除き、年齢のみとなっています。例えば、「1類試験(大学卒業程度)」は、大学卒業(見込)者が対象ではなく、問題の難易度が大学卒業程度という意味です。
質問:過去の試験問題は公表されていますか。
回答:過去の問題は公表していませんが、同等の分野・程度の問題を例題として公表しています。例題については、こちらでご確認ください。
採用・配属
質問:最終合格をしても、採用されない場合がありますか。
回答:競争試験の最終合格者は、人事委員会が作成する採用候補者名簿に登載され、その中から任命権者(知事、教育委員会、警察本部長)が、採用面接を行った上で採用者を決定します。本県の場合、合格者は例年ほぼ全員採用されております。しかし、試験に合格しても採用されない場合があります。
質問:配属先について教えてください。
回答:配属先については、はたらく環境の「キャリアパス」の項目をご覧ください。
給与・勤務条件
質問:勤務時間等について教えてください。
回答:勤務時間等については、はたらく環境の「勤務条件・ワークライフバランス」の項目をご覧ください。
質問:初任給について教えてください。
回答:初任給については、はたらく環境の「勤務条件・ワークライフバランス」の項目をご覧ください。
なお、ホームページに掲載されていない職種については、各受験案内でご確認ください。
研修制度
質問:研修制度はどのようなものですか(知事部局の例)
回答:研修制度については、はたらく環境の「研修制度」の項目をご覧ください。
質問:メンター制度はどのようなものですか(知事部局の例)
回答:メンター制度については、はたらく環境の「新規採用職員への支援」の項目をご覧ください。
※その他、質問や不明な点があれば、人事委員会事務局までお問い合わせください。